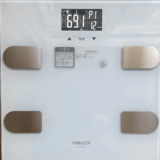「同じランチを食べたのに、私はすぐ太るのに友人は全然太らない」―そんな経験はありませんか?
ダイエットをがんばっても成果が出にくいと「自分の努力が足りないのでは?」と落ち込みがちですが、実はそこには体質や遺伝、腸内環境の違いが関係しているようです。
今回は「栄養の吸収効率」と「体質」の関係を見ていきながら、体格や体質ごとのダイエットの工夫、さらに誰にでも役立つ“腸内細菌の育て方”をご紹介します。
腸内細菌の違い
近年の研究では、腸内細菌のバランスが太りやすさに直結することが分かってきました。
たとえば、腸の中には「ファーミキューテス門」と「バクテロイデーテス門」という2大グループがいて、前者が多いと食べ物からエネルギーを効率よく吸収しやすく、後者が多いと余分なカロリーを排出しやすいのです。
つまり、同じ食事をしても腸内細菌の比率次第で太りやすさが変わるというわけ。実際に、肥満マウスの腸内細菌を“痩せ型”の無菌マウスに移すと、そのマウスも太ってしまったという実験報告もあります。
「太る・太らない」は、食事量だけでなく“腸のパートナー”に左右されるのです。
遺伝的な違い
さらに、体質の背景には遺伝もあります。
たとえば肥満関連で有名な「FTO遺伝子」。ある変異を持つ人は、そうでない人に比べて平均3kg体重が重くなる傾向があると報告されています。
ちなみにFTO遺伝子とは、「肥満関連遺伝子」として最もよく知られているもののひとつで、ガソリンをため込みやすいタンクを持っている車みたいなイメージ。同じ量を食べても、効率よくエネルギーを吸収して“脂肪として貯金”してしまう体質です。
また、日本人に多い「β3アドレナリン受容体遺伝子」の変異型も要注意で、基礎代謝が低め=“省エネ体質”になりやすいことが分かっています。
このβ3アドレナリン受容体遺伝子は、脂肪細胞にある「スイッチ」のような遺伝子で、体が脂肪をエネルギーとして燃やすかどうかに関わっています。燃費が良すぎるストーブみたいなイメージで、同じ量の燃料(食事)を入れても、あまり燃やさずにストック(脂肪)します。日本人では約3割がこの変異を持っているとのこと。
でもこれは「悪い」ことではありません。飢餓が当たり前だった昔なら、省エネ体質こそが生き延びる武器でした。昔なら…。
消化吸収の違い
胃腸の強さも、栄養吸収効率に影響します。胃酸や消化酵素がしっかり出る人は、食べた栄養を無駄なく取り込みます。逆に胃腸が弱い人は吸収効率が低いため、同じ量を食べても太りにくい傾向があります。
「太りやすい」と聞くとマイナスに感じるかもしれませんが、言い換えると“燃費のいい体”です。
歴史を振り返れば、人類はほとんどの時代を飢餓と戦ってきました。その中で「少ない食料からしっかりエネルギーを確保できる体」は圧倒的な生存力を持っていたのです。
これは「倹約遺伝子仮説」と呼ばれ、実際に糖尿病やメタボのリスク遺伝子の多くは、昔なら生き延びるための“選ばれし特徴”だったと説明されています。昔なら…。
だからこそ現代社会でダイエットに悩むのは皮肉ですが、**自分の体質は弱点ではなく“歴史に裏打ちされた強み”と考えてみましょう。うれしくないかも、ですが。
こういった、努力ではどうにでもできないことがあることをふまえつつ、じゃあ実際にダイエットしたい!となった場合、体質・体格によってどんなことをすればいいのかを考えていきましょう。
(1)筋肉質タイプ(燃焼型)
代謝が高く太りにくい一方、油断すると内臓脂肪がつきやすいタイプ。
👉 有酸素より筋トレを重視し、タンパク質をしっかり取って筋肉量を維持するのがポイントです。
(2)脂肪をため込みやすいタイプ(省エネ型)
食べたものが脂肪になりやすく、空腹時間が長いとさらに「節約モード」に入ってしまいます。
👉 極端な食事制限は逆効果。低GI食品を中心に、小分けに食べるスタイルがおすすめです。
(3)胃腸が弱いタイプ(吸収効率低め)
太りにくい代わりに栄養不足になりやすいタイプ。
👉 無理なダイエットは厳禁。消化に優しい食品を選び、タンパク質・鉄・ビタミンB群など不足しやすい栄養素を意識的に補いましょう。
体質や遺伝は変えられませんが、腸内環境は改善できます。実際に「食生活を変えると、腸内細菌はわずか1日で反応を示す」との研究報告もあります。
発酵食品をとる
納豆やヨーグルト、味噌汁などは、腸に善玉菌を直接届ける働きがあります。スタンフォード大学の研究では、発酵食品を意識的に摂った人は腸内細菌の多様性が増し、炎症マーカーが下がったと報告されています。
食物繊維を増やす
野菜・海藻・きのこ・オートミールなどは腸内細菌のエサになり、腸内環境を整えます。特に「冷やご飯」に含まれるレジスタントスターチは、善玉菌を増やす効果が高いことでも知られています。冷やご飯でも、ご飯はご飯。ちゃんと美味しいですよ。
血糖値の急上昇を防ぐ
主食を玄米や雑穀米にしたり、野菜を先に食べる“ベジファースト”を実践するだけで、血糖値の上がり方は20〜30%抑えられることが分かっています。
規則正しい生活リズム
腸内細菌には「体内時計」があり、夜更かしや不規則な食生活は腸内環境を乱します。7〜8時間の睡眠と、できるだけ同じ時間に食事をとる習慣を意識しましょう。
(ちなみに…)腸内細菌を育てると得られるメリット
腸内環境を整えることは、ただ「太りにくくなる」だけではありません。研究の積み重ねにより、次のような幅広い効果が確認されています。
- 体重管理:短鎖脂肪酸の働きで脂肪がつきにくくなり、満腹感も得やすくなる
- 便通改善:腸の動きが整い、便秘が解消されやすくなる
- 免疫力アップ:腸は最大の免疫器官であり、感染症やアレルギー予防に関与
- 心の安定:腸内細菌がセロトニンなどを介して気分に影響し、ストレス耐性を高める
- 生活習慣病予防:血糖値や血中脂質を安定させ、糖尿病・動脈硬化のリスクを下げる
つまり腸活は、美容・健康・メンタルを同時に整える習慣。
ダイエットを成功させたい人だけでなく、誰にとってもプラスになる「全身の健康投資」と言えるのです。
5. まとめ:太りやすさは“体質”の要素も大きい
- 太りやすさの50〜70%は遺伝や腸内環境など体質の影響
- 「太りやすさ」は欠点ではなく、歴史的には生き延びるための強み
- ダイエットは「自分の体質に合った工夫」をすることが近道
- 誰でもできる共通の対策は「腸を整える生活習慣」
「努力が足りないから痩せられない」のではありません。体質を理解し、腸を味方につける―これが健康的に長く続けられるダイエットの秘訣です。
私も励みます!